死体写真やマニュアルによって浮かび上がる“死のリアリティ”願望
“死の書”ブームは精神世界の行き着く先か。
所載:『アクロス』1994年2・3月合併号
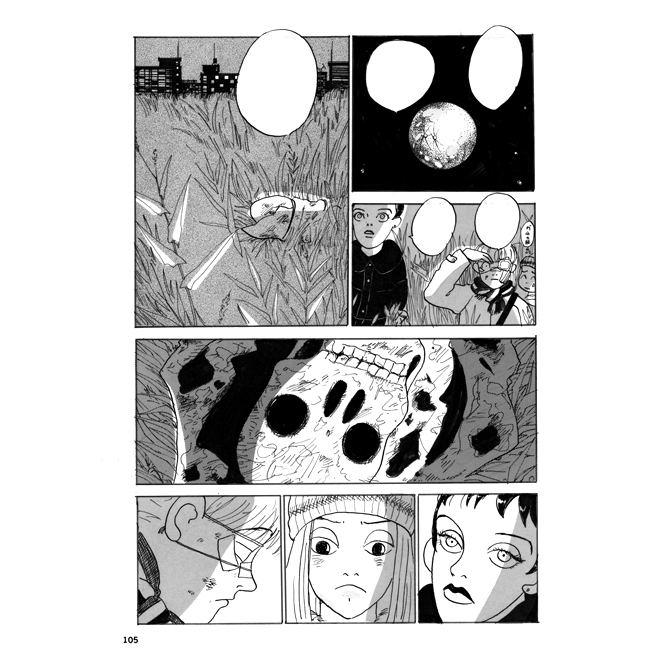

- 布施英利著『死体を深せ!』『図説・死体論』
- 鶴見済著『完全自殺マニュアル』
- 河邑厚徳・林由香里著『チベット死者の書』(バルド・トドゥル)
- 「ゴタクはもう聞き飽きた」(『完全自殺マニュアル』より)
- 関連リンク
時代は、世紀末であるらしい。この時期になると、死の臭いが濃厚となり、終末論的なムードが盛り上がるのが歴史の常である。エイズというこれまで人類が経験したこともなかつた新しい病の流行が世紀末という空気に拍車をかけているということもあるだろう。例えば、“死"をテーマにした書籍が売れ筋であるのも、“世紀末”の反映であると、とりあえず短絡してみたい。
代表的なものは表に挙げた通りである。
〈93年に出た、“死“をテーマにした本9冊〉
●布施英利「死体を探せ! バーチャル・リアリティ時代の死体」法蔵館
美術評論家であり解剖学者でもある著者が、死体をめぐつて、自らの経験やメディアなど様々な角度からの考察を展開する。
●布施英利「図説・死体論」法蔵館
「死体を探せ!」のビジュアル版。一見キワモノ的な写真集といった感じだが、構成が緻密で、自然と“読む"ことを促される。
文字通り“完璧”を目指した自殺の手引書。弱者への同情が行間にほの見える。全て自分のこととして書いたと著者は語ってくれた。
●河邑厚徳・林由香里「チベット死者の書 仏典に利められた死と転生」NHK出版
アメリカン・ドラッグカルチャーと「死者の書」が出会ってから、エイズ末期
患者の死の床に至るまでの過程が興味深い。
●式田和子「死ぬまでになすべきこと」主婦の友社
主婦向け投稿誌の編集長だから書けた、等身大の“老い”と“死”のマニュアル本。淡々とした筆致に、宗教書にはない感動がある。
日本における分子生物学の草分けが、“死”という現象について語る。冒頭の自身の死への恐怖についての赤裸々な告白がいい。
富山で発刊され、全国的なベストセラーに。納棺人という死者に接する職業の
著者が“死”を見つめ続けた思索の書である。
“死"をめぐるエッセイといった趣だが、殺人や自殺の現場とおぼしき写真に吸い寄せられる。死者の、静謐な息づかいが聞こえる。
●小池寿子「屍体狩り」白水社
ョーロッパの中世美術から煙草のマークまで、死の図像を題材に綴られたエッセイ集。著者は「死の舞踏学会」唯一の東洋人会員である。
これ以外に、脳死、臓器移植、ホスピス、ターミナルケア、臨死体験などに関するものを含めるとかなりのものになる。“死”をテーマにしたコーナーまで設けている書店もある。医療の現場からアートの領域にわたって、これほど広範囲からのアプローチで死が語られたことがかつてあっただろうか。過去、死を扱った本のジャンルを見ればわかるように、これまで死は、宗教的・哲学的・観念的なものとして語られてきた。人間にとってこれはど普遍的で、誰もが必ず体験するとても具体的な現象が、きわめて高踏的で難解で、それこそ日常から遊離したものとして捉えられてきたフシがある。
ところが現在は、死に対するアプローチが多様であるばかりでなく、ある種の傾向として、死を、即物的かつ具体的なものとして見つめ、等身大の平易な言葉で語ろうとする志向が読み取れる。よリダイレクトに直接的な体験として認識しろと促す書物が多いことに気づかされる。それはしばしば死体写真集やマニユアルといった、これまでにない体裁をとったりする。
例えば表に挙げた『死ぬまでになすべきこと』は、「老いるとは尿瓶の助けを借りること」という章に始まり、遺産相続、老人ホーム、墓、献体と、死ぬまでのプロセスで知っておくと便利な情報を集めたマニュアル集だ。そこには“神話”もなければ“ロマン”もない。現代の“死”のありようが、明快に提示されている。今まで“尿瓶”といったきわめてリアルなものを起点に“死”が語られたことがあっただろうか。
現在の死には、もはや高尚な“哲学”は必要ない。あるがままに見つめ、それをどう受けとめるか。考え選択するのはその人の自由だ。そのような“実践の書”をいくつか取り上げ、そこに語られた“死”のあり方を見てみたい。
布施英利著『死体を深せ!』『図説・死体論』
(死体標本や解割の光景など、ギヨンとするようなビジュアルに添えられた文は至ってシンブルだ。それが一層、死体そのものを際立たせる)
論考を中心としたテキスト版『死体を探せ!』と、そのビジユアル版『図説・死体論』の2冊が対になった書物である。後者のあとがきの中で著者の布施英利氏は次のように述べている。「(死体写真や絵を)じっと見つめてほしい。見つめているうちに図版が語りかけてくる声が聞こえてくるだろう。その声(それこそが死体論なのだ)に耳を傾けてはしい。(略)現代を、都市を救うのは、死体だ。死体こそ、これから僕たちが生きるうえでもっとも大切な『思想』なのだ」
布施氏のこうした姿勢は、ビジュアル版だけでなく、『死体を探せ!』とも共通している。すなわち、著者は“モノ”でもなく“人間”でもない“死体”をあるがままに直視し、日常に取り込むことによって、今世紀初頭より隠蔽されてきたところの“死”(フィリップ・アリエス『死と歴史』)を、現代という時空間に復権させようと試ているのだ。“死体”の“思想”を語るのではく、“死体”そのものが“思想”であるとする直裁な主張がある。
『死体を探せ!』には、著者の自殺死体目撃談から、解剖学、図像学、歴史、アート、犯罪、メデイア論、都市論などの様々な視点から“死体”にまつわるいろいろな事象が語られている。その根底に流れているのは解剖学者として日々死体に向き合い、解剖という「肉体労働」を通して培われた「健全な」認識である。80年代初頭、藤原新也がインドで撮影した、犬に食べられる人の死体の写真が話題になったが、ちょうど藤原がインドという“自然”が剥き出しの場所で“死体”という“思想”を獲得したように、著者も解剖学を通して藤原と同じ“思想”を得たということであろう。
死体に接するようになって「精神が“健康”になったかもしれない。思想上の変化はない」と答えてくれた著者だが、“死体”を通して現代人(とりわけ日本人)が「健全」さを回復することこそこの本の著者のメッセージだと理解した。
「この国に欠けているものは『死体感覚』にほかならない。日本の『都市』は、死体に代表されるような『自然』をひたすら排除する。それを私たちは『脳化』と呼んでいる。脳化都市では『自然』は実体を失い、電子の映像などとなって氾濫する」
そこで“自然”を取り戻すために、「プラスティネーション」と呼ばれる技法で処理された死体写真に親しむことが有効であるとする主張がなされる。死体写真といい、加工された死体標本といい、キワモノ的な嗜好と混同されてしまう危険があるのだが、著者はそこにはっきリ一線を引く。ホラービデオなどに代表されるその手の表現は、“死”や“死体”を直視しない人々の幻想の産物だというのだ。研究室にある標本を見て、「『キヤーキヤー騒いでいる』のは、たいてい『見ていない人』だ」という著者の主張は、死に関するテーマヘのマスメディアの反応にそのままあてはめて考えることができるだろう。
88年の連続幼女誘拐殺人事件の容疑者が好んだとされるスプラッタービデオなどのソフトを総称して著者は「電子の幽霊」と呼ぶ。なるほど、「脳化都市」をイメージ化すれば、さながらM容疑者のおびただしい数のビデオテープに囲まれた部屋ということになるであろうか。
「電子の幽霊」が経験として不十分なのはわかる。しかしそれらのキワモノ的なメディアと、加工された死体標本や死体写真集との決定的な差異を説明することは、今のところ困難だと言わざるを得ない。現代の都市に“自然”を取り戻すには、まだまだ様々なかたちの“死体”が必要だということだろうか。
(※書名のない引用は全て『死体を探せ!』より)
鶴見済著『完全自殺マニュアル』
(青木ヶ原の自殺者の遺品から見つかり話題になった『完全自殺マニュアル』。テレビを始めマスコミの反応は、概ね“マニュアル”という表層部分を字義通りにとらえた批判的なトーンのものだった)
「有害図書」の指定をめぐって論議されたり、各メデイアにも大々的に取り上げられ、昨年大変話題になった本の1冊である。ちなみに前述の布施英利氏はこの本についてこうコメントしている。
「かつて『死体は語る』という本がベストセラーになったが『完全自殺マニユアル』もそれと同じで、いかに死んだか(死ぬか)ということがポイントになっている。僕の本は(死因はともかく)死んでしまった後の死体を扱っている。別の主題だ。/あまり指摘されないが『完全自殺マニユアル』が売れたのは、彼に文才があるからだと思う」
確かに“死”と向き合うベクトルに違いはあるだろう。『自殺マニユアル』は“死”(あるいは自殺)そのものを問題にしない。“死”を一つの事象としてカッコに括り、「コトバによる自殺装置」と帯にあるように、一粒の毒薬として読者に提示する。それをどう使うかは読者の自由なのだ。しかしその毒薬を手にとって見ているうちに、死がきわめて身近なものとして感じられるようになる。隠蔽されたはずの“死”がリアルに立ち上がってくるのだ。つまり“死”を直視するべし、と啓発する点では布施氏の著作と共通するものがあると言えるのではないだろうか。
文才について言えば、彼のドライで時折ブラックユーモアを感じさせる文体は、著者がよく読んだという初期の村上春樹を紡彿とさせる。民族学者の大月隆寛は、書評で「80年代ニヒリズムの影」を指摘している.(「ダカーポ」12月15日号)。
今から11年前に刊行された『自殺 もっとも安楽に死ねる方法』(1983年)というフランス人の書いた本の翻訳が『自殺マニュアル』を書くヒントになったというが、実際この本、自殺論とぃった社会学的な考察が主で、自殺の手引きの部分は巻末に申し訳程度にあるだけなのだ。必要なのは分析ではない。「今必要なのは、自殺を実践に移すためのテキストだ」(序文)。そしてより徹底して実用的な本書が出来上がったというわけである。
著者は学生時代、人並みにニューアカの洗礼を受けたと語る。「現代思想をやってないと話が通じないって感じでしたからね。だけど今から考えると、あれは何だったんだろうなって思いますね。結局答えはなかったじゃないか。ただの言葉の遊びじゃなかったのかって」
“言葉”や“思想”や“分析”では、最早インパクトを与えないのではないかという疑間があったに違いない。読者に直接作用するマニユアルという形態が最も有効なのではないのかと(この点は初期の山崎浩一に影響を受けたという)。
著者が、主にテレビなどの取材を受けた際、「なぜ若者は自殺に走るのか」といったような質問が一番多かったそうだ。あるいは、このての本を書いたことに対する社会的責任を問うような糾弾調のものもあったという。やはりお茶の間では、いまだに
“自殺”=“不健全” “反社会的"という図式から離れられないということだろうか。しかし一方、実際、読者からの反応は、「生きる勇気がわいた」的な感想も少なくなかったという。逆説的に心の支えとなりうる本書は、著者が狙った通り、生きているのか死んでいるのかわからない「延々」と続く退屈な日常に風穴を開けることにいくらか成功したと言えるのではないか。
河邑厚徳・林由香里著『チベット死者の書』(バルド・トドゥル)

昨年の9月23・24日、2日間にわたって放映されて大反響を呼んだ、NHKスペシャルのタイアツプ本である。著者は番組を制作したプロデユーサーの河邑厚徳氏。河邑氏が1981年に制作した番組に『ドキュメント・がん宣告』がある。今から14年前のこの番組が、『チベット死者の書』を企画するに至る出発点となったと氏は語る。
『がん宣告』は、一人の会社員ががんを宣告され、聞病の末亡くなるまでを記録したドキュメンタリーである。まだ告知も一般的ではなかった時代にあって、ドキュメントという形式で、人が死にゆく様を扱ったのはきわめて異例であり、衝撃的だ。日常の中の等身大の“死”を、真正面から取り上げたのは、おそらくテレビ史上初の試みであったろう。
「この番組の取材中、末期のがん患者の苦脳を目の当りにして、結局最後は苦しんで死んでいくわけですけど、すごく救いがない感じがしたんですね。スタツフもみんなノイローゼみたいになっちやつて。僕自身、人の死の最期の姿がとても悲惨なものに感じたんです」
本来、人は家で死んでゆくものだったのが、1977年より病院で死ぬ人の数がそれを上回るようになる(91年で、75.9%の人が病院で死んでいる)。“死”が日常から消えてしまう時期であり、もちろん“死”などもないに等しい時代だった。河邑氏は番組終了後、もっと違う死に方はないものかと考えるようになる。そしてこの時期、インドヘ取材に行くチャンスがめぐってくる。
「藤原新也さんの写真と同じように、ガンジス川で大に食われる赤ん坊の遺体を見たんです。一応撮影もしましたけど。死が当たり前のようにあるインドで、病院で死んでいった彼とはまた違う“死”に触れて、心の重荷が降りたという感じでした。それですべてが終わりじゃないという、輪廻転生の世界が、インドでは現実のものとしてあったんです」
『がん宣告』の後に“死”を扱うとしたら、次のステップを表現したかった。それが西チベットのラダックで、死者を送るために現在も用いられている経典、「チベット死者の書」をテーマにした番組に結実したというわけだ。
この番組で画期的だったのは、死体が頻繁に登場したという点である。『がん宣告』ではラストに主人公の死の直後の映像が象徴的に一瞬使われていたに過ぎず、当時テレビではそれが限界であった。その点で時代の変化を感じさせると河邑氏は言う。
もう一つ印象的だったのは、ラダックで死後行われる儀式が、ただの“未開の地の奇妙な風習”といった風にならないように、アメリカのダイイング・プロジエクトを紹介したことである。サンフランンスコのホスピスの現場で、実際に「チベツト死者の書」を用いている現状は、これが現代においても有用な実践の書であることを証明している。
この経典には死後、人が遭遇するであろうこと、そしてどうすればよいかという「安らかに死ぬための技術」が詳細に記されている。エイズや高齢化社会の到来を契機に、この“究極の実用書”が脚光を浴びたのは、偶然でない。「死者の書」は、“死”が隠蔽された時代において、直接体験的に死と向き合うための手引きとして有効なガイドだということができるだろう。
この番組の反響から、今後マスメデイアが“死”を取り上げていく機会が多くなっていく予感がある。
「ゴタクはもう聞き飽きた」(『完全自殺マニュアル』より)
布施英利氏は、「チベット死者の書」にある死後に人間が見る様々な光明をテレビの光になぞらえている。また鶴見済氏も「テレビを消したあとの、あの奇妙な暗さを覚醒させる」のが本の狙いだといっている。そしてNHK版『チベット死者の書』の共著者である林由香里氏は、自分たちの世代は“体験”を奪われた世代であり、「ブラウン管を突き抜けると別世界が広がるという幻想があって、パッと死ぬとその瞬間に別世界が開けて、そこに希望を見出すというようなところはあるかもしヤしない」と言う。
1960年代に生まれたこの3人が、いずれも死について語るときにテレビの体験を持ち出しているのが興味深い。彼らは生まれたときからテレビがあったメデイア世代であり、“死”の存在しない「電脳都市」に育った世代である。だからホラーなどのキワモノに対する抵抗のなさがエスカレートして、現在、“死”をダイレクトに即物的に見つめようとする志向が生じたのか。あるいは高度成長によって崩壊してしまった、本来“死”を支えたはずの村落共同体的な共同幻想の代わりに、自分達の手によって“死”を再構築しようとする意志が芽生え
たのか。理由づけはいくらでもできるだろう。しかし、「ゴタクはもう問き飽きた」のである。例えば『自殺マニュアル』の序文にあるように「身ぶるいするような日常生活」のグロテスクさと、そこから脱するための最後の自由としての自殺というような考え方は、大江健三の『われらの時代』などですでに取り上げられているテーマだ。事実“死”は普遍的なテーマであるし、時代的な問題というよりも、それを取り上げ扱う感性の質の問題なのかもしれない。
取材に際しても、『死体を探せ!』と『完全自殺マニユアル』の著者は、共に安易な世代論や解釈を婉曲に拒んでいるように感じられた。それは無理もないだろう。しかし、臓器移植、脳死、ホスピスなどの医療の現場からの要請によって、あるいは高齢化社会の到来によつて、我々が否応なく“死”に直面せぎるを得ないであろう現実を、彼らが鋭敏に感じ取っていることは間違いないようである。
「地球上のどの民族も、かつてはメメント・モリ(死を想え)を出発点として独自の精神文化を作り出して」(『チベット死者の書』)きたのだ。そして現代の社会において、“死”は日常から隔離され、隠蔽されてしまった。時折偶然その“断片"を目撃する程度である。“死”が隔離されることに比例して、我々の“生”もまた希薄なものとなってくる。“生”も“死”も宙づりにされてしまう。そちらの方がむしろ異常な事態なのだ。
そこで、自分自身の手になる“死”(自殺)を通して、あるいは具体的な“死体”を通してそれを実感するしかない。それが今現在の「メメント・モリ」だし、新たな精神文化のありようなのだ。できれば見ないで済ませたい、としてタブー視してきた死を直視する、という流れが生まれてきたのは、現代日本人の精神が成熟に向かいつつある現れなのだと考えられないだろうか。

