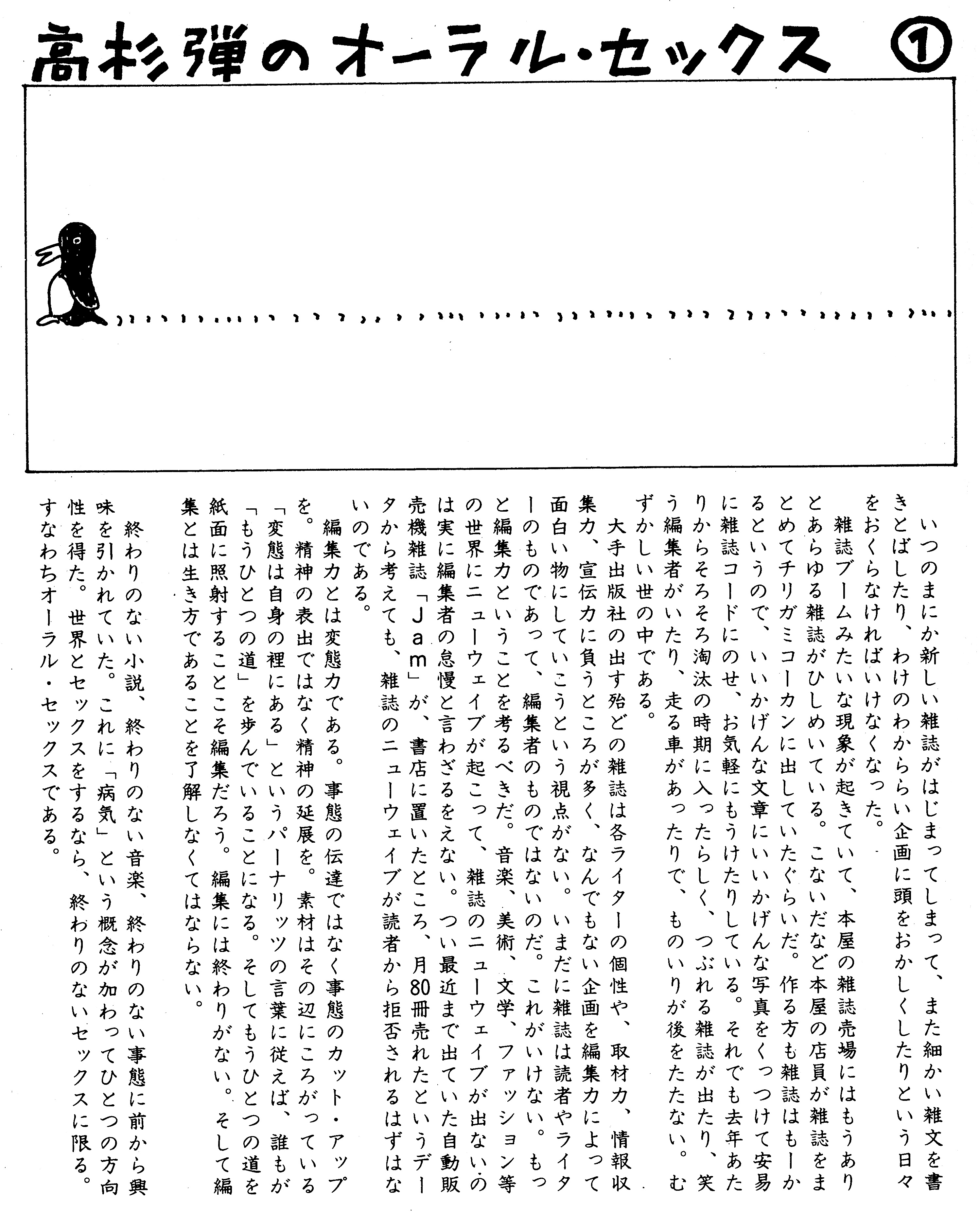この記事にリダイレクトします。
チャンネル争い史—三丁目の猟奇
チャンネル争い史ー三丁目の猟奇
はじめに
テレビの「チャンネル争い」は誰しもが(たぶん)経験する、家族間での代表的な揉め事であった。「あった」という過去形から、まず結論を言っておこう。「チャンネル争い」という家庭内紛争は少なくとも日本国内では、ほぼ終戦状態である。
もっとも、チャンネル争いは一台のテレビのチャンネル権を家族内の誰かが占有するという条件/状況下で発生するもので、現代でもないとは言い切れないが、すでにテレビは「一家に一台」から「一人一台/一部屋一台」という時代になり、そもそも娯楽多様化でテレビそのものを見なくなっているという人も多い。
だが、昭和中~後期まではビデオデッキも普及してなかったし、「録画して後で見る」ということはまず不可能で、ゆえにこの頃が最もチャンネル争いがヒートアップしていた時期であるといえよう。
ここでは、過去の新聞報道から国内のチャンネル争い史を振り返ってみよう。
1960年「毒薬入りウイスキー事件/大阪」
国内のチャンネル争いについて、『朝日新聞』や『読売新聞』といった全国紙では1963年頃からチャンネル争いに起因する「事件」を報じている。
しかし、チャンネル争いを扱った国内における最古級の記事は『毎日新聞』1960年(昭和35年)5月11日付・東京朝刊5頁に掲載された「深刻なチャンネル争いーテレビと家庭の問題」という記事である。
この記事内では冒頭にチャンネル争いに起因する大阪の殺人事件を紹介している。
最近、大阪で見たいテレビ番組のことで姉とけんかし、父にしかられてなぐられた男の子(一三)=中学三年生=が、この父をうらんで、ウイスキーに毒薬を入れて殺してしまったという事件がおこりました。
警察の調べによると、もちろん少年には“殺意”というものはなく、病気になって病院にいけばうるさくなくなるというほどの気持ちからだったようです。それに少年も平素の素行もよくなく、父も酒のみという特別な事情があったようです。それがテレビチャンネルの争奪というきっかけで爆発してしまったといえそうです。それにしてもテレビのチャンネル争いは、多かれ少なかれどの家庭でもみられることです。
のちに紹介する事件にも共通することだが、チャンネル争いに関係する事件は、チャンネル争いに敗れたことが「引き金」となって鬱憤が爆発し、殺人、傷害、自殺に発展するケースが目立つ。
されど、こうした諸々の問題を抱えた家庭において、致命的な「事件」が起こるというのは遅かれ早かれ、時間の問題だったろう。事件のきっかけとなる「チャンネル争い」なんて、結局のところ、事件を起こす動機の一要因に過ぎないのである。
ちなみに注目すべきは堀秀彦*1が寄稿した以下のコメントであろう。
テレビがうんと安くなって個室にテレビが置かれ、自由に好きなものが見られるようになれば(この結果どんな人間が生まれるか別問題として)この問題は解決するが、それまでは、いまのままではいつまでも多かれ少なかれつきまとうのではなかろうか。
結果的に堀の予言は的中することになるが、この予言が実現するまでには3、40年は待たねばならない。
また堀の「個室にテレビが置かれ、自由に好きなものが見られるようになれば(この結果どんな人間が生まれるか別問題として)…」という一文であるが、事実、現代の小中高生の多くはポケットに収まるスマートフォンで、親の目を離れては「好きなもの」を自由気ままに見れるようになっている。またその結果「どんな人間が生まれた」かも、皆様はよく御存知であるはずだ。
1978年「中二の兄、小六の妹刺す。両親、共働きの留守/埼玉」
1978年(昭和53年)4月20日夕方、埼玉県与野市で、木曜日の夕方5時に日本テレビで再放送されていた『さるとびエッちゃん』を中学2年生の兄が、小学6年生の妹はTBSで再放送していた『みつばちマーヤの冒険』を見たいと喧嘩。
以前からふたりの間には喧嘩が絶えなかったらしく、兄の鬱憤が爆発、チャンネル争いの末に妹を果物ナイフで刺殺、ビニール袋を被せて段ボール箱に死体を入れてから警察に通報して自首するという事件が起こる。
(Wikipediaより一部改稿)
この事件はWikipediaにも記載されているほか『毎日新聞』『読売新聞』『朝日新聞』『週刊サンケイ』など主要紙でも報じられ、当時は結構話題になったらしい。
(毎日新聞 1978年4月21号 東京朝刊 23頁)
事件翌日には、東京都小金井市立小金井第二小学校の六年三組で本事件に合わせてチャンネル争いにまつわる「学級討論会」が開かれた*2。
以下、チャンネル争いにまつわる子供たちのエピソードをそれぞれ列記する。
「大学の姉さんとけんかして、ブラウン管まで割っちゃった」と男子。「取り合っているうちに、チャンネルのつまみが壊れた」と女の子も負けない。
「兄ちゃんにいつもぶたれるよ」
「二年生の妹を突き飛ばしたら、障子がはずれてしまった」
「みそ汁をひっくり返したことがある」
「プロレスで決着をつけることにしてるけど、戦ってるうちに番組が終わってしまうんだ」
その紛争を、家庭内では、どうやって解決しているか。体操着の男の子が不服そうに「うちのお母さんはいつも『あんたは兄さんだから我慢しなさい』という」と発言すると、賛同の拍手。
「いい合いをしてると、うちの母さんは『二人とも外に出て考えなさい』と追い出してしまう」「ナイターを見たいお父さんとけんかしてると、最後はお母さんが入ってきて自分の好きな番組にしてしまう」という報告もあった。
ちなみにチャンネル争いで「けんか」をしたことがある六年三組の児童は出席39人のうち38人、実に97%にのぼった。
なお、解決方法に「テレビ2台論」や「ビデオデッキ」を求める児童の声もあったが、それに対して先生は「やはり高度成長時代に生まれた子ですね」と苦笑いし、「欲しいものは何でも買える、もらえる、という発想はこわいな。昔の子は我慢、あきらめ、という美徳を持っていた」とぼやかれになられた。
正直、年長者に多い「我慢と忍耐」を美徳とする日本人的根性論をこんな場面でも持ち出されるとは、正直辟易とさせられるのだが、こうした世代間でのジェネレーションギャップは今も昔も変わりはない、ということか。
1980年「中一の弟、中二の姉を射殺/徳島」
(読売新聞 1980年2月4日号 東京朝刊23面)
1980年(昭和55年)2月3日、徳島県三好市(現・三好郡東みよし町)で中1の弟が中2の姉を父の散弾銃で射殺した“昭和の田舎で起こり得るであろう最悪なチャンネル争い事件”が発生した。以下事件の内容である。
2月3日午後7時、地元の警察署に「姉を猟銃で撃ち殺した」という110番があった。
同署員がAさん宅にかけつけたところ、Aさん方の階下六畳間で少年B(13)が立ちすくんでおり、足下に長女C子(14)さんが散弾銃で頭を撃ち抜かれ血まみれになって倒れていた。C子さんは約10キロ離れた県立病院に運ばれたが、出血多量で死んだ。
Bの自供によると、姉弟二人はこの日の午後二時すぎからテレビを見ていたが、バレーボールの試合を見たいというC子さんに対し、Bが漫画番組を見るといって譲らずけんかになった。その後もチャンネルをめぐって口論を続けた結果、Bは父親の銃を持ち出し、姉に一発発砲した。銃は階下の勉強部屋にあった。
近所の人の話では、Aさん一家は五年前、二階建て約60平方メートルの家を新築、その支払いのため父親は茨城県内の建設作業現場に出稼ぎに行き、母親は同郡池田町内で飲食店を経営、毎日通っており、祖母(65)が姉弟の世話をしていた。姉弟の仲はよかったという。
猟銃は父親が昭和50年9月、許可を受けて購入した単発銃で、出稼ぎ中は銃を分解、二階の部屋のキャビネット式の保管庫に入れて施錠、隠していた。しかし、Bはカギと弾薬の隠し場所を知っており、銃も自分で組み立てていることから父親が銃を扱うのを見ておぼえたらしい。
Bは日ごろ家に猟銃があるのを自慢にし、最近も友達を呼んで見せびらかしていたという。
とにかく少年Bがクソ過ぎると思ったが、まあ好奇心旺盛な中学生の悪ガキに本物の銃を与えたら、こうなっても仕方ないのかなと思える。普通、人間は頭に血が上ったら「脅し」で包丁や銃を持ち出すことはあるとしても、情緒が欠落した小中生は本当に刺したり撃ったりするからコワイ。なんの解説にもなってませんが(笑)元々仲良しの姉弟だったという点で前掲した埼玉の事件より残酷に思える。
また同時期には小学生男子がいたずら目的で幼女を殺害してしまった事件もあったことから、記事内には「東に西に凶悪犯罪の低年齢化」の現状を憂いた文章も書かれていた。(文◎虫塚虫蔵)
高杉弾インタビュー「ぼくはプロの編集者であったことなどなかったし、むしろ編集者に変装した変質者でした」
何人?高杉弾
数々の伝説を生み出した、あの80年代ニューウェーブ雑誌『Jam』『HEAVEN』の編集長にインタビュー
高杉 弾氏、現在、青林工藝舎 アックス編集長 手塚能理子氏。
— 滝本淳助 (@takimotos1) 2015年5月20日
高杉氏、元気なの❓フォローぐっと来たよ。 pic.twitter.com/5XwjyD1TBV
追体験は無益なことだろうか? 理解への一歩は追体験ナシにははじまらない。だから過去にこだわりたい。自販機雑誌『HEAVEN』は過去の遺物だ。しかしそれを振り返らなければならない現実は今、ここにある。テーマは自らを追体験することにある。そして今現在の自分をいかに理解するかだ。『HEAVEN』の1コラムにそのヒントを見つけたいと思うのである。
いつのまにか新しい雑誌がはじまってしまって、また細かい雑文を書きとばしたり、わけのわからない企画に頭をおかしくしたりという日々をおくらなければいけなくなった。
雑誌ブームみたいな現象が起きていて、本屋の雑誌売場にはもうありとあらゆる雑誌がひしめいている。こないだなど本屋の店員が雑誌をまとめてチリガミコーカンに出していたぐらいだ。作る方も雑誌はもーかるというので、いいかげんな文章にいいかげんな写真をくっつけて安易に雑誌コードにのせ、お気軽にもうけたりしている。それでも去年あたりからそろそろ淘汰の時期に入ったらしく、つぶれる雑誌が出たり、笑う編集者がいたり、走る車があったりで、ものいりが後をたたない。むずかしい世の中である。
大手出版社の出す殆どの雑誌は各ライターの個性や、取材力、情報収集力、宣伝力に負うところが多く、なんでもない企画を編集力によって面白い物にしていこうという視点がない。いまだに雑誌は読者やライターのものであって、編集者のものではないのだ。これがいけない。もっと編集力ということを考るべきだ。音楽、美術、文学、ファッション等の世界にニューウェイブが起こって、雑誌のニューウェイブが出ないのは実に編集者の怠慢と言わざるをえない。つい最近まで出ていた自動販売機雑誌「Jam」が、書店に置いたところ、月80冊売れたというデータから考えても、雑誌のニューウェイブが読者から拒否されるはずはないのである。
編集力とは変態力である。事態の伝達ではなく事態のカット・アップを。精神の表出ではなく精神の延展を。素材はその辺にころがっている「変態は自身の裡(うち)にある」というパーナリッツの言葉に従えば、誰もが「もうひとつの道」を歩んでいることになる。そしてもうひとつの道を紙面に照射することこそ編集だろう。編集には終わりがない。そして編集とは生き方であることを了解しなくてはならない。
終わりのない小説、終わりのない音楽、終わりのない事態に前から興味を引かれていた。これに「病気」という概念が加わってひとつの方向性を得た。世界とセックスをするなら、終わりのないセックスに限る。すなわちオーラル・セックスである。
(アリス出版『HEAVEN』創刊号「高杉弾のオーラルセックス」より)
高杉 前回東京の某誌からインタビューの連絡を受けたのも二年前のコサムイ滞在中で、FAXで返送した回答の補足を、バンコクのワット・ポー境内からGSMで長電話したことをよく憶えています
最近は一年の半分近くを海外で過ごす隠居生活を送っており、日本の友人とさえ音信不通の日々ですが、まだぼくのことなどを覚えている見知らぬ人がいるのですね。不思議な感覚です。東京に滞在しているときでさえ日本人マインドから遠く離れて久しく、自分の位置を自らナビゲートしなければ、まともに生きていくことさえおぼつかない毎日です。
さて、20年も前に『メディアになりたい』という本を出してしまっているぼくにとって、すでに〈メディア〉になどあまり興味がなく、ひたすら気になるのは〈メディアマン〉の消息だけです。このニュアンスをご了解いただければ幸いです。
───高杉さんが「自販機本時代」に編集された『Jam』とその後の『HEAVEN』は、相変わらず古本屋価格ではべらぼうな値段が付けられていますが、自分で持ち込んでプレミア価格で買い取ってもらったりしたことはありますか。なければさぞかし悔しい思いなのではないかと思うのですが…。
高杉 他誌の前回のインタビューもそうでしたが、また20年も昔の話ですね。『Jam』も『HEAVEN』も、過去の自分が戯れに作っていた物で、「過去の自分」など現在の自分から思えば他人同然ですから、これからぼくは「他人」について語らねばなりません。しかし、他人について語るのは自分について語るよりよほど面白いし、しかも楽だ。
『Jam』や『HEAVEN』が古本屋でかなりの高値で売られていることは、知人などに聞いて知ってはいました。しかし、自分の目で確かめたわけでもないし、もちろん売りに行ったことなどありません。そもそも、ぼくは『Jam』や『HEAVEN』を数冊しか持っていません。美沢真之助が死んだときに、全冊揃えるのに苦労したほどです。
それにしても、あんなものにプレミアを付けて高値で売り、それを買う人がいるなどということ自体が狂っている。深夜、退屈しのぎに見る自販機本ですよ。しかも20年も前の。「さぞかし悔しい思い」ですって? 人を舐めるのもいい加減にしていただきたい。ぼくは、そんな「架空の金銭」と交換する仕事をした覚えはありません。
───「いつのまにか新しい雑誌がはじまってしまって、また細かい雑文を書きとばしたり、わけのわからない企画に頭をおかしくしたりという日々をおくらなければならなくなった」(以下引用はすべて『HEAVEN』創刊号「高杉弾のオーラルセックス」より)
「自販機本時代」から「AV監督時代」などを経て「MEDIAMAN」となった高杉さんとしては、最近ではどのようなメディアに面白さを感じますか。また、今はどのようなわけのわからない企画などに頭をおかしくされているのでしょうか。
高杉 「高杉弾のオーラルセックス」という連載をしていたことさえ完全に忘れていたので、そこに書いていたことについて聞かれても、なんだか「今さらなあ」という感じを否めません。
つまり、ぼくは20年前からプロの「編集者」であったことなどなかったし、むしろ、編集者に変装した変質者でした。変質者が一時的な退屈しのぎに好き勝手な紙の切り張りをしていた。要するに、ゴミをカットアップしたスクラップブックですね。それに程々のお金を払い、それなりに楽しんでくれた人たちがいた、というだけのことでしょう。
ぼくが「わけのわからない企画に頭をおかしくしたり」とか、メディアがどうのこうのと偉そうに語っていたとしたら、それはもう若気の至りというものでしょう。はっきり言って、若い頃のぼくは単なる「馬鹿」です。
ですから、「今はどのようなわけのわからない企画などに頭をおかしくされているのでしようか」というご質問にはお答えしにくいです。わけのわからない企画どころか、「わけのわからない世界」に常に頭がぐらぐらになっています。昔のぼくは単なる「馬鹿」でしたが、今のぼくは「人間のクズ」です。これに関しては、確実に自覚があります。
外から日本を見ると、日本という国は完全に気が狂っていて、もはやどこの国からも相手にされていない「終わってしまった国」のように感じます。
世界が興味を持っているのは、日本ではなく日本円です。しかし世界は常に激動している。日本人の田舎臭いマインド・レベルは、もうどこの国に行っても通用しないでしょう。人間のクズと自覚しているぼくとしても、もう日本という国にはあまり興味が持てなくなっています。
興味のあるメディアといえば、「人間の脳味噌またはマインド」としか答えようがありません。
───「雑誌ブームみたいな現象が起きていて(中略)作るほうも雑誌はもーかるというので、いいかげんな文章にいいかげんな写真をくっつけて安易に雑誌コードにのせ、お気軽にもうけたりしている」
90年代中ごろからのPCの成熟安定化と廉価化によって、雑誌はそれをつくる手段がほぼPCに移行し、i-Mac一台でもカンタンにつくれるほどに安易なものになってしまいました。しかしそのクオリティはといえば、その横着が悪いかたちで表われてしまい、合理的な文章、合理的な画像、合理的な企画で安易な内容のビジュアル重視のものがさらに増えてまったような気がしますが、それについてはなにか思いますか。
高杉 端的に申し上げて、「インターネットなど、もう古い」ということでしょう。インターネットはその発展と同様に、ものすごいスピードで「過去の遺物」になりつつあります。ぼくがずっと以前から言い続けていたのは「人間の脳味噌こそが地上唯一最大のメディアである」ということです。コンピューターに代表されるデジタル文化など、日本人洗脳の道具にしかすぎないということなど、心ある人ならすでに気づいていることです。
そもそも「合理的な物の考え方」などという貧しい発想が現在の地球を混乱に陥れているのは自明の理です。黒人を400年間奴隷にし、搾取して富と利権を蓄え、「合理主義」という窮屈で陳腐な思想が蔓延してクレイジーなデジタル信仰と経済原則がまかり通っている日本や西欧世界に、もう未来などありません。
日本人も陳腐な白人思想にかぶれてしまい、メディアという言葉をはき違えてきたように思います。腐ってしまった味噌や豆腐に毒物を添加して作った味噌汁を「あまり美味しくないなあ」と無自覚に思いながら食べているのが日本人の現実です。「洗脳は舌から」、これがGHQ以来の戦略だったのでしょう。そして、メディアや文化についても同じことが言えるのです。
───「大手出版社の出す殆どの雑誌は各ライターの個性や、取材力、情報収集力、宣伝力に負うところが多く、なんでもない企画を編集力によって面白い物にしていこうという視点がない。いまだに雑誌は読者やライターのものであって、編集者のものではないのだ」
いわゆるインディーズ・マガジンをやっている連中というのは、その部分にたいするアンチテーゼの意識がある者もいれば、発行者の自己顕示欲を満たすためだけのものなどさまざまです。そこでお伺いしたいのですが、大手出版社誌がこれだけ読者(返品率)に強張り、淘汰に怯えるという現実において、雑誌は「編集者のもの」になりうるのでしょうか。また、そういった意味でインディーズ・マガジンには存在意義があると思いますか。
高杉 この問題は大手出版取次店の存在を抜きには語れないでしょう。そして、ぼくは当初から雑誌を「大手出版取次店のもの」にしてしまう日本の出版事情にはまったく興味がありませんでした。せめて雑誌は「編集者のもの」であって欲しかった。
それから時は流れて「インターネットの時代」。しかし、ぼくがWEB上に作った〈JWEbB〉という雑誌でさえ、すでに一度リムネットの検閲を受けて一方的に全ページ削除(契約破棄)という理不尽な手段に出られた経緯があります。日本に言論、表現の自由など、もともと無いのです。そのことを、若いインディーズ・マガジンの編集者たちにもはっきりと自覚していただきたい。
そして、「媒体」などにかかわらず、人間は生きているだけで〈メディア〉です。アナログからデジタルに移行し、「発行」が「発信」に変わったからといって、それがいったい何だというのか。完全に文字化けした日本語を「世界に発信」して、いったい何の意味があるのか。
───「音楽、美術、文学、ファッション等の世界にニューウェイブが起こって、雑誌のニューウェイブが出ないのは実に編集者の怠慢と言わざるをえない。(中略)雑誌のニューウェイブが読者から拒否されるはずがないのである」
ニューウェイブが起った80年代については、今では忌み嫌う声ばかりです。高杉さんにとって80年代とはどんな時代でしたか。
高杉 80年代に自分が何をしていたのか、ほとんど覚えていません。雑誌に雑文を書き散らしていただけのような気もしますし、毎日大麻やコカインを吸ってラリっていただけのような気もします。ロサンゼルスやサンフランシスコで豪遊していたのも80年代だったかな。重要なのは「時代」ではなく、「ムーブメント」でしょう。
しかし、日本の雑誌界にニューウェイブはもう永遠にこないでしょうし、逆に、コンドームのように使い捨てられる雑誌ほど売れるでしょう。ぼくには、もうどうでもいいことです。ただ、日本の80年代でもっとも重要なのは、日本が企業社会主義国になった、ということだけでしょう。
───「編集力とは変態力である」
これを今ドキのバカギャルにもわかるように説明してやってもらえませんでしょうか。
高杉 「今ドキのバカギャル」などにはまったく興味がありませんし、彼女らに教えることなど何もないと思います。ぼくには「バカギャル」というのがどのような女性を指す言葉なのかも把握できていません。「編集力とは変態力である」などと書いたのは、メディアマンではなく高杉弾というウツケ者でしょう。「編集力」も「変態力」も、今のぼくには日常の埒外です。
───「終わりのない小説、終わりのない音楽、終わりのない事態に前から興味を引かれていた。これに『病気』という概念が加わってひとつの方向性を得た。世界とセックスするなら、終わりのないセックスに限る。すなわちオーラル・セックスである」
名文であります。ところで、なにげなーく拠点をコサムイに移されているように見えまが、コサムイにはどんな終わらないものがあるのでしょうか。
高杉 もともと「拠点」などという発想を持ったことはありません。拠点って、なんだか左翼の活動家みたいで気持ち悪いじゃないですか。コサムイは、ただ気候的に気持ちのいい場所なので行っているだけで、それもせいぜい年に2、3か月程度です。海と、椰子のジャングルと、馬鹿な白人観光客用バンガローと、不味いレストランがあるだけの島です。
コサムイに限らず、気候的に温暖で、物価が安く人々が仏教徒で温厚であれば、ぼくの周囲に「終わりのない世界」はすぐに出現します。タイは今年2544年です。バリのサカ暦はそれ以上でしょうし、そんなことにさえ関係なく、南国には南国の「寛容な空気」が流れています。そして、これこそが日本にはない一番重要なものなのです。
バンコクやコサムイやウブドの部屋で目覚めるぼくの日常は、それこそ終りの無い日々。その日何が起きるのか予想さえできませんし、明日何をするのかなんて考える気もしません。死ぬまで続くそういう日々の連続が「終りの無い世界」への夢を増幅させるのだと思います。多くの人々が「金銭」やら「デジタル」やら「情報」やら「健康」やらといった幻想にうつつを抜かしている間に、ぼくは気持ちのいい夢を見ることにしただけなんです。
───雑誌とインターネット。高杉さんにとって両者はどのように違いますか。
高杉 雑誌はメディア、インターネットは「情報」の運び屋、つまり運送屋でしょう。新幹線ができて、ちょっと便利になったのとあまり変わりませんね。ぼくはもう雑誌にもインターネットにも何の期待感も抱いていません。そんなものはもう古い。過剰に管理されるメディアなんて、もううんざりだ。
数年前に「脳内リゾート開発」という概念を提供しましたが、できることならもっと多くの人々に、人間がもともと持っている優秀なアナログ機関である脳味噌の、未開の部分に注目していただきたい。気楽に、柔軟にね。
───今後高杉弾及びMEDIAMANは新しい雑誌などを仕掛けられる予定はありますか。
高杉 雑誌にもデジタル・メディアにもあまり興味がありません。最後に唯一読んでた『太陽』も休刊になってしまったそうだし。ぼくは気楽で暇な隠居の身です。もし日本に面白い雑誌があるなら、お教えいただきたい。
自分で印刷媒体を作ることなどないでしょうし、デジタルなんかもともと信用していない。そんなことをしなくとも、世界の現実は雑誌以上に面白いですよ。
それから、〈メディアマン〉というのは特定の個人を指す名ではなく、「高杉弾という個人に内臓されるメディアとしての脳味噌」を経由して表現されるすべての事象に因んで公案された〈概念〉であると理解していただきたい。
(所収:ラクダ・パブリシング『創的戯言雑誌』2000年刊/絶版)
高杉 弾(たかすぎ・だん)
東京品川生まれ。4歳から9歳まで、川崎市等々力の水郷地帯で蓮の花に囲まれて育つ。1979年から1980年にかけて自販機雑誌『Jam』『HEAVEN』の編集長として数々の伝説を生み出す。
現在は"メディアマン"というコンセプトのもとに言語アーチスト、作家、編集者、企画家、観光家、ステレオ写真家、臨済禅研究家、蓮の花愛好家、ラリ公などと呼ばれながら"MEDIAMAN"としての国際的な隠居生活を楽しんでいる。競馬と散歩と昼寝、南の島やタイ・香港旅行が道楽。毎年11月~3月はバンコク、サムイ島、バリ島、香港のいずれかにいることが多い。
雑誌、単行本、インターネット等のメディアに突発的な仕事を発表することもある。仕事は一貫してジャンルではなくマインドで選び独自の世界観からの発言や表現活動を極めて気まぐれに続けている。金銭的利益追求を第一義とするマスコミや出版業界は大嫌い。
脳内リゾート開発事業団所属。ステレオオタク学会会員。〈imperialMEDIAMANinternational〉代表。
娘が遺した日記と漫画で「教育」見詰め直す―漫画家・山田花子の自殺
連載[師走の街から](7)
娘が遺した日記と漫画で「教育」見詰め直す
五月の運動会から数日後のことだった。四年生を担当する女性教諭(50)が三十四人の教え子たちに手紙を託した。
〈これからは、子供たちの声にならない声に、もっともっと耳を傾けていきます〉
先生はおかっぱ頭。やせてはいても、東京郊外の小学校で「一番の元気者」を自慢にしていた。ところが、運動会が近づいたころ、長女が飛び降り自殺してしまった。手紙は、この悲しい出来事を静かに見守ってくれた父母たちにあてて書いたものだった。
長女は二十四歳、漫画家だった。「山田花子」のペンネームで、一時、「週刊ヤングマガジン」や月刊「ガロ」などに連載を持ち、単行本も二冊出していた。人間関係の息苦しさや疎外感を強調した漫画だ。内向的で感受性の強い主人公がいじめにあい、傷ついていく。遺(のこ)された十五冊の日記帳は、主人公が作者自身で、描くことで生きるつらさを乗り越えようとしたことを物語っていた。
日記や漫画を読んで先生はがく然とした。自分そっくりの教師が主人公に言う。「あなた、お友達がいなくて淋(さび)しくはないの」。確かに、友達が少なかった娘を同じ言葉でよく送り出した。日記の中の娘は一人で時間をつぶしては自ら服に泥をつけ帰宅していた。初めて知った。
教師歴二十八年。「いろんな子がいて当たり前。弱い子も強い子も個性を生かしてあげなきゃ」が口癖だった。いじめや登校拒否にも体ごと取り組み、二人の娘を育てた。「自由を口にしながら自分の型にはめようとしていたのか」
それから、追われるように仕事をした。救いは死後も絶えない読者からの手紙だった。「悩んでいるのは自分一人ではなかったと力づけられた」「私の人生を変えるのは山田花子かもしれない」
愛読していたという人気バンド「たま」の知久寿焼(ちく・としあき)さん(27)は、霊前で「自分の姿を見るようで身につまされた」と涙を流した。これほど人の心を動かした「山田花子」の感性とは何だったのかと考えるようになった。
夫婦で娘のことを本にまとめようと決めた。毎晩、日記や作品、彼女の聴いたテープ、愛読書を整理する。書き始めたばかりの目次には大きく「学校といじめ―教師と母親の構造」とある。
「娘の供養ではなく、自分がこれから生きて行くために書き上げなくちゃ」と、先生は思う。(若江雅子)
(おわり)
所収:『読売新聞』1992年12月25日号 東京夕刊
山田 花子(やまだ はなこ、1967年6月10日 - 1992年5月24日)は、日本の漫画家。本名、高市 由美(たかいち ゆみ)。
自身のいじめ体験をベースに人間関係における抑圧、差別意識、疎外感をテーマにしたギャグ漫画を描いて世の中の矛盾を問い続けたが、中学2年生の時から患っていた人間不信が悪化、1992年3月には統合失調症と診断される。2ヵ月半の入院生活を経て5月23日に退院。翌24日夕刻、団地11階から投身自殺。24歳没。
青林堂創業者/漫画雑誌『ガロ』初代編集長・長井勝一インタビュー「世の中から差別をなくすことを、底の底に持った雑誌を出版していこう」
生前最後のインタビュー
「漫画雑誌『ガロ』会長・長井勝一(現代の肖像)」
- 『ガロ』編集長・長井勝一「貧しかったけど、心は貧しくなかったよな」
- 「白土三平さんと会うまで金もうけりゃいいってね、漫画本出してた」
- 「世の中から差別をなくすことを、底の底に持った雑誌を出版していこう」
- 南伸坊「渡辺和博がよくいうんですよ、学校みたいだったよな」
- 漫画雑誌『ガロ』が30年間続いた秘密は
- 付記「青林堂に関連する一連の報道について」(山中潤)
『ガロ』編集長・長井勝一「貧しかったけど、心は貧しくなかったよな」
漫画家・白土三平に口説かれた。「漫画雑誌をやろう」。忍者漫画を通して人間の本質を描く白土の真摯さに、本気になった。
水木しげる、つげ義春───。思想をもった作品を生んだ『ガロ』は、創刊者長井の度量が人をひきつけ、作家の個性を伸ばした「学校」でもあった。
土曜日のある夜、長井勝一(ながい・かついち)宅を一組の夫婦が訪れた。4コマ漫画の、あの勝又進である。長井は、さっそく自宅近くの天ぷら屋で一席設けた。
「授賞式に遠くから来てくれてありがとうな」
長井は小柄な体を縮め、かすれた小さな、少し高めの声でお礼をいう。勝又は恐縮する。
今年の6月下旬、長井は第24回日本漫画家協会賞の特別賞をもらったばかり。漫画雑誌『ガロ』を30年以上も発行し、多くの漫画家を発掘、育てたのが、その理由である。勝又もまた、作品発表の場が『ガロ』であった。学生と機動隊の衝突を、明るくのんびりと描いていた。
長井はキスの干物を手でむしり、食べながら、つぶやいた。
「これ、うまいなぁ。……魚に骨がなければ、もっといいのにな」
こんなことをいう人は初めてだ。勝又に、「長井さんは、どんな人ですか?」と水を向けると、
勝又が照れ笑いを見せ、
「オヤジさんという感じ。こうして顔を見るだけで安心するんです。実家に来るみたいですね」
と、話し終わるや、「来れば、おれも楽しいさ」と、長井は、うれしそうにいう。
長井が『ガロ』を創刊したのは、1964年7月24日である。B5判130ページで定価130円。東京オリンピック開催の2カ月半前だ。創刊号からスタートの予定であった白土三平の『カムイ伝』が登場したのは、4号目の12月号だった。
勝又は、隣の長井をちらりと見て、「『カムイ伝』が始まったあとでしたね。いつも、『ガロ』の編集部にいりびたっていたんですよね。松田さんも学生で上野さんも、みんな遊びに行っていた」と話す。
「貧しかったけど、心は貧しくなかったよなぁ。漫画が好きだ、描きたいという人が集まってきた。それでいて、人まねなんかしたくない人ばかりでなぁ」
長井は淡々とした口ぶりだ。
「それでいて、長井さんにはなんでもいえましたね」
勝又が、そういうと、
「おれはエバルような人とは付き合わないよな。いまでもそうだ」
長井はなんでもないようにいう。あまり飲んではいけない酒を口にしながらである。一滴一滴を、本当にうまそうに飲むのだ。
二人の間で名前の出てきた、松田さんは筑摩書房の松田哲夫、上野さんは評論家・上野昂志である。そんな『ガロ』を舞台にした漫画家を少しあげてみる。白土三平、水木しげる、つげ義春、楠勝平、勝又進、池上遼一、永島慎二、滝田ゆう、佐々木マキ、林静一、つげ忠男、矢口高雄、高信太郎、やまだ紫、近藤ようこ、蛭子能収……。作家・赤瀬川原平もいる。評論家・呉智英もいる。井上迅もいる。編集部育ちでは、南伸坊、渡辺和博たちがいる。
個性的な顔と、その作風が浮かんでくる。目がくらむようだ。集団として徒党なんて組むことのない、まさに群像である。
『ガロ』育ちの人たちを、評論家・鶴見俊輔は次のように表現する。
「戦後の学問の歴史でいうと、今西錦司さんの作った今西学派というのはたいへん大きなものですが、そうした区分を超えて思想史を考えるとき、ガロ学派は今西学派に匹敵すると私は思っています」
“ガロ学派”───。鶴見はこうもいう。
「『ガロ』は漫画雑誌というだけでなく、一種の総合雑誌としての気分を持っている。これは、初期から上野昂志さんが『目安箱』というコラムを書いていることでもはっきりしている。とても鮮やかな評論で『中央公論』や『世界』の評論より鋭いっていう場合がある。そういうのを出し続けていった雑誌でもあるわけで、そこに出てくる漫画も思想性がある」
「白土三平さんと会うまで金もうけりゃいいってね、漫画本出してた」
戦後という時代について、ふと考えるようなとき、今後に思いをはせるとき、『ガロ』の人たちの影響力は無視することは出来ない。
それを育てたのが出版人・編集人の長井勝一である。だが、長井は、アッケラカンと語る。
「創刊してから、ぼくが現場にいたころまで、編集会議なんて一回もしたことなんてないんです。会議をしたっていう奴がいたら、インチキだよ。ナベゾ(渡辺和博)にしたって、南(伸坊)にしたって、ぼくの顔なんて見ませんよ。好きなようにやっていた。『来月号は誰と誰の漫画を載せる』。これだけ。ワンマンなんかじゃないんですよ。編集会議するような雑誌じゃないもの。原稿並べるだけなら誰でもできますよ」
それから、右手の指でマルを作り、
「これの話はよくやったよなぁ」
と、妻の香田明子に確認する。香田は、遠慮気味に「ウーン」と、うなずく。彼女は、『ガロ』発刊以前からのパートナーで、経理をみてきた。

こんなエピソードが語り継がれている。南伸坊が編集部にいたころである。
「そりゃあそうだよ、人間だからな」
長井の口癖だ。人間だから失敗することもあるし、人をだますことだってある。
原点は50年前の8月15日である。日本は敗れた。腹の奥では、いままでの日本はないと思う。だが、人間の日常は同じ。飯を食べトイレにもいく。ナーンも変わらない。理屈ではない。それだけだ。
そして、その2日後、長井は浅草に出来た露店の一角に店を出した。捨てられた雑誌をバラし、表紙だけを新しくしたものを売るのであった。それがなくなると、クズ屋に出た漫画本を、適当に束ねなおして売る。途中に別の漫画が飛び出してくる代物だ。これが売れたのだった。娯楽なんてない。子どもへのお土産である。人間はいい加減なのだ。オレもそうだった。
ある日、長井に南が、「人間だから、といったって毛沢東はエライんじゃないですか」といった。「この名前さえ出せば、一本取れる」。南はそう思った。毛沢東という名前に全く意味はない。世間で有名だったからだ。返ってきたのは、
「毛沢東だって、人間だからな……」
返品されてきた単行本のカバー替えをしながら、そういったという。
長井によると、こうである。
「人間って、誰もさ、日常に流されるじゃない?たとえ孔子だって流されるよ」
長井勝一は、大正10(1921)年生まれだから、今年で74歳である。4年前の91年、『ガロ』発行元の青林堂を身売りし、会長になった。『ガロ』の顔としての名誉職だ。それ以来、経営にも編集にもタッチしていない。長井に30年前の回想をしてもらう。『ガロ』発刊の動機だ。“ガロ学派”が生まれる舞台の始まりでもある。
「白土三平さんと出会うまで、金もうけりゃいいやってね、漫画本を出してたんです。バクチはするわ、女とは遊ぶわ。ところが、三平さんの漫画を制作する態度をみていて、自分もきちっとやらなきゃと思うようになったんです」
戦後の体験から、そのまま漫画出版の世界に入る。56年、「日本漫画社」を始め、翌年の夏の終わりごろ、白土三平に会う。
出会いは、いつも必然である。貸本屋に卸すため、仕入れた漫画本のなかから、面白い本を見つけたのであった。白土の『こがらし剣士』である。ストーリーがいい。絵もいい。どんな人だろう。一週間後、長井のもとに、その白土三平が作品を持ち込んできたのである。返事はもちろんオーケーだ。白土は、「ここでもし、ダメだったら、もう漫画を描くのはやめよう」と思っていた。出会いは偶然、とよくいうが、そんなことはない。相思相愛がある。長井は、「願ってもない偶然」と振り返る。看板は白土の作品にした。貸本屋向けの単行本『嵐の忍者』『甲賀武芸帳』を立て続けに出し、59年暮れには、『忍者武芸帳』第1巻の刊行を始める。
「世の中から差別をなくすことを、底の底に持った雑誌を出版していこう」
長井勝一・白土三平コンビによる作品にいち早く注目したのが、のちの文化人類学者・山口昌男である。60年6月のある雑誌で、こう書いている。
「私の近所の貸本屋でも(白土三平は)人気ベスト・ワンであり、子供たちの中に割り込んで新作を借り出すのは仲々困難である」
白土作品の特徴として、上手な漫画、人間的な息吹、忍者をテーマにして組織の残酷さの強調などをあげ、「大人のマンガがエロのムードに酔っている時、残酷非道のムードを導入して単にそれによっているのではない白土の世界の方が、人間世界の把握では却ってその先のところにあるのかもしれない」と記している。
だが、『忍者武芸帳』刊行途中に、長井は結核で倒れた。七本の肋骨を切るという大手術を受けたのだった。
「『忍者武芸帳』を最後まで出せなくてね。入院中、これまでぼくは何をしてきたんだろうと思うと力が抜けていくような感じになって……。これでは、死んでも死に切れないと、ね」
退院してきた長井に、白土は「雑誌をやろう」ともちかけてきた。単行本には読者に限りがある。雑誌には広がりがある。そういった。
「三平さんの大きなテーマは、いわれなき差別をなんとかしていこうということが願いなんです。その思いを大勢の人にわかってもらいたいと思っていたんじゃないでしょうか。『カムイ伝』がそうですよね。それに、その頃はいまと違って、漫画は日陰の状態にあって、これを日向に出すというか、文化の面にまで押しあげることはできないだろうかといったんです」
記憶をたどるという様子は、全くない。長井にとって忘れようにも忘れることのできない話だ。
「普通なら仕事が切れれば縁の切れ目だけど、三平さんは、ぼくの手術代から入院中の小遣いまで出してくれてね。三平さんと話しているうちに、ぼくは『できる』と思ったんです。もう、いいかげんな気持ちじゃなくなっていました。漫画のいい作り手を育てよう。『ガロ』の骨子は、新人を育てること、漫画の水準を押しあげること、それに世の中から差別をなんとかなくしていくことを、どこか底の底に持った雑誌を出版していこうと二人で話し合ったんです」
雑誌の名前は、すぐ決めた。白土作品に『大魔のガロ』がある。長井によると「心優しく、技量のすぐれた忍者だったが、その優しさを逆手にとられ、彼になついた子どもを使った術にかかって悲惨な最期を遂げた忍者」だ。そこからとったのである。

『ガロ』創刊である。すでに「青林堂」という出版社を作り、白土の『サスケ』を出していた。その売り上げを資金に発行するのである。白土は、翌年の65年6月号で「おのれの実験の場として、この『ガロ』を大いに利用していただきたい」との、文を載せた。実験と刺激の空間である。それを求めて、人は集まってきた。反響は意外なところからもやってくる。雑誌もまた人である。出会いを作っていく。
「私は、白土三平氏の漫画を大変おもしろく、且つ、貴重なものと思いながら、愛読しています。私は、京大経済学部の大学院に在籍し、マルクスの革命思想を研究し、公式的な石頭的公認マルクス主義の再生を日夜祈りながら勉強しております」
同年11月号、『ガロ』が行った「読者の感想文特集」の一通である。投稿の主は竹本信弘。これから7年後、全国に指名手配を受けることになる、全共闘運動のリーダー・滝田修である。大学生が漫画を手に取り、熱中する。その始まりが『ガロ』である。部数も創刊時の8千部から、66年暮れには10倍に伸びた。もちろん、多くの新人が登場してきた。
書籍取次店「トーハン」の出版調査機関・出版科学研究所によると、漫画についてのデータを取り始めたのは七六年からだという。出版刊行点数で、それを外して考えられなくなってきた。市場が急激に膨れ上がり、漫画の量産体制が始まっていたのだ。大手資本出版社の本格的な参入だ。零細企業にとって厳しさは増すばかりである。この2、3年前から『ガロ』は部数が減り始めてきた。『カムイ伝』も第一部が71年7月号で終わっていた。長井風にいえば、右手の指でマルを作ることが多くなってきたのだ。
南伸坊「渡辺和博がよくいうんですよ、学校みたいだったよな」
毎月、資金繰りに追われる。税務署から、「管轄外ですが、もう少し、社員の給料を上げたらどうですか」といわれたこともある。しかし、会社をつぶすわけにはいかない。援助してくれた漫画家の人たち、印刷、製版関係の人たちがいる。なによりも、「これをやめて、お前になにが残るのか」と励まされるとピリオドはうてない。だが、とうとう力尽きて、91年、倒産よりもと身売りを選んだ。
「いまは天国みたいなもんです。こうして、起きては好きな山本周五郎や司馬遼太郎の本を読んでるだけですから。会社をやってたときは地獄ですよ」
白土三平は昨年9月号の『ガロ』で、長井さんがいたからこそ『カムイ伝』が描けたという。普通の雑誌社だったら、ストーリーにクレームをつけただろう、と。
南伸坊は、「ナベゾ(渡辺)がよくいうんですよ。『ガロは学校みたいだったよな』って」と話す。南が編集者として『ガロ』にいたのは、72年から7年間だった。入社して、いきなり写植をまかされた。台割りで凝ると、長井が近寄ってきて「あんまり凝らないでなぁ、南」とささやいた。夏の暑い日、クーラーがないので、長井が「もういいか、今日は」というと、そのまま、みんなで銭湯に行った。
「ほら、学校で、先生が今日は外で遊ぼうか、ってあるでしょう、そんな感じでした」
雑誌『ガロ』で、作者に自由に描かせるのと同じ空間が編集部だった。勝又も松田も気ままに遊びに来ていた。南も、長井のことを「オヤジのような人」という。「長井さんに、自分のことがわかってもらえるのがうれしい」。“ガロ学派”は、「自分の好きなことをやる」と「長井さんにわかってもらうこと」が見えない校則かもしれない。人が人に出会う。すでに手垢にまみれてしまった、この言葉が、よみがえってくる。
出会いは次の出会いを用意する。9月、松田哲夫は『頓知』という新しい雑誌を創刊する。アートディレクターは、南伸坊だ。松田は創刊に向け多忙な日々が続いている。初めに考えた部数の2倍の数字を取次が出してきたそうだ。反響の大きさに驚いている。
長井勝一の周辺でいつのまにか出来上がった群像は、キーパーソンに満ちている。有名というのではない。何かが始まり、何かを始める、そんなときに“カギ”になっている人のことである。扇子を開いたときの要である。
(文中敬称略)
*
長井勝一=ながい・かついち(1921~1996)
青林堂の創業者であり、漫画雑誌 『月刊漫画ガロ』の初代編集長。
白土三平や水木しげるといった有名作家から、つげ義春、花輪和一、蛭子能収、矢口高雄、滝田ゆう、楠勝平、佐々木マキ、林静一、池上遼一、安部慎一、鈴木翁二、古川益三、ますむらひろし、勝又進、つりたくにこ、川崎ゆきお、赤瀬川原平、内田春菊、丸尾末広、ひさうちみちお、根本敬、南伸坊、渡辺和博、みうらじゅん、杉浦日向子、近藤ようこ、やまだ紫、山田花子、ねこぢる、山野一、泉昌之、西岡兄妹、東陽片岡、魚喃キリコといった異才までを輩出していった名物編集長として知られる。
*
文・中川六平=なかがわ・ろっぺい(1950~2013)
ライター。編集者。1950年、新潟県生まれ。同志社大卒。学生時代、山口県岩国市で反戦喫茶「ほびっと」を経営。卒業後、新聞記者を経てフリー。日本の近代史に関心を持ち、雑誌『マージナル』編集長を務める。編著書に『天皇百話』(共編)など。2013年、逝去。
(所収『AERA』1995年8月28号)
漫画雑誌『ガロ』が30年間続いた秘密は

『ガロ』。奇妙な月刊誌名である。白土三平の忍者漫画からもらった。
忍者「ガロ」は、優しさがあだとなって悲惨な最期を遂げた。「大好きな話だったんですよ」
1964年に創刊、20日には30周年の会が開かれた。
『ガロ』が育てた個性は多い。つげ義春、林静一、佐々木マキ、川崎ゆきお、蛭子能収……。「自分の感覚に合う作品を載っけただけなんです」。並外れていようとキラリと光る何かさえあれば、と。
「長期的な経営戦略はなかったねえ。その月、その月、好きなことでとりあえず食ってければいいってね」
大学生にも一目置かれ、67年、68年には8万部刷った。時代が熱かったころだ。しかし、70年代半ばに、部数はがくんと落ちた。原稿料を払えない状態が当たり前になった。
「楽しい思い出ねえ、うーん、浮かんできませんね。命を削るようにしてかかれた作品なのに、お金が出せなくて、悪いなあ、つらいなあってことばかりで」
「かかせてくれ」との申し出を、材木屋二階の編集部でひたすら待つ毎日。それでも芽吹き間近の才能が長井を慕い、『ガロ』の人間味を求めて集まった。何度か襲った雑誌存続の危機にも、どこからか支持者が現れた。
「私の方が漫画家に面倒みてもらってきた感じです」
3年前、山中潤社長に編集も経営も任せた。「お酒と本をやっと楽しめるようになりました」。ただし、今の漫画はまず読まない。
「漫画出版はお化けみたいな規模になっちゃった。その割に気の利いたものは少ない。若い人は活字離れするし。自分のやってきたことは良かったのかなんて思うけど、しょうがないよね。自分の器量では、ここまでがいっぱいいっぱいだから」
(文・鈴木繁)
所収『朝日新聞』1994年8月23日号
*
「『ガロ』やる前は、金もうけもうまかったんですよ」。73歳。
付記「青林堂に関連する一連の報道について」(山中潤)
2017年2月14日に『ガロ』元編集長である山中潤さんの声明が発表されました。以下全文のテキストを記載します。
創業者長井勝一氏および青林堂の株主総会より正式な認証を得て青林堂を受け継いだものとして、最近の報道について、きっちり申し上げる責任があると思い、ここに記すことにいたします。
私は長井氏より「青林堂はカムイ伝を連載するガロを出版するために作った」そして「ガロは差別を無くすために生まれた雑誌だ」という言葉をはっきりと聞いています。テーマも漫画家もいわゆるメジャー漫画誌では扱わないような「社会から零れ落ちそうな物を掬う」ということが根底にありました。
ガロに掲載された、芸術的作品も、面白主義や、差別や不条理を様々な方法で描いた作品も、全ての作品の根源には「カムイ伝」や「長井勝一の創業の精神」があります。
私もその魂を継続、拡大することが役目と思い、1990年より97年まで青林堂代表取締役兼編集長の職に挑んだつもりです。
会長の職に就いて頂いていた長井氏が96年に亡くなり、当時私が経営していたツァイトというパソコンソフトウェアの会社もWindowsの登場により、海外ソフトとの厳しい競争にさらされ、右肩上がりとは言えない状況ではありました。
そのとき、私をコンピュータの世界に引き上げたF氏にツァイトの社長を交代してもらい、私は青林堂に専念する事に決めました。ツァイトは自分で創立した会社だけれど、青林堂は私が預かっている“文化”であり、自分の事情でつぶすなどしてはならないと、本当に思っていました。
ところが、ツァイトの社長を頼んだF氏の父親が亡くなられ、F氏は心のよりどころを関西のO氏にゆだねるようになります。O氏は青林堂に興味を示し、青林堂の株式を取得するようにF氏を動かし始めました。
その様子が見えてきた時点で、私はF氏から距離を置くため、当時青林堂の株式を所有していた私の個人会社の印鑑を持って、極力東京から離れるよう努めました。
しかし、今、思い出しても胸が痛いのですが、私はF氏の様々な工作に乗せられ、無理やり青林堂まで腕づくで連れて行かれ、当時青林堂の実印と青林堂の株式を保有していた会社両方の実印をF氏に取られました。
その夜のことは、新聞などで大きく報道されたようですが、私は再度東京を離れたので、その後、ツァイトが私の社長名で倒産をしたこと以外は、詳しくわかりません。
その後の編集部の独立や新会社設立、その後の青林堂の動向は、内部の人間としてではなく、外部の人間として知る事になります。
とは言え、そこで踏ん張りきれなかったことは私の責任であり、今でも大きな悔恨として日々生きております。
報道されている現在の青林堂の社長であるK氏やW専務とは、97年以前より交流はありましたが、それは私個人の範囲であり、編集部との付き合いは極めて薄く、長井氏とは面識もありません。
つまり、現在報道されている青林堂は名前は同じであっても、創業者長井勝一氏とはまるで関係のない、単に株式を取得した人間が、元々の青林堂やガロの精神とは関係のないところで行っている全然別の事業に過ぎず、元々の『ガロ』とは無関係です。
私より、かつてのガロ・青林堂を愛して下さった、読者・作家・関係者、そして『ガロ』を今でも愛し続けてくださるファンの皆様が、様々な誤解や偏見に晒されることもあるかと思いましたのでこのような文章を記させていただきました。
『ガロ』元編集長・山中潤
図版
➀青林堂『月刊漫画ガロ』1971年12月号表紙(画・林静一)
②水木しげる『私はゲゲゲー神秘家水木しげる伝』角川文庫、2010年、194頁
④高信太郎『ミナミトライアングル 解決編』(青林堂『ガロ』1977年6月号)
⑤青林堂『月刊漫画ガロ』1992年8月号表紙(画・山田花子)
⑥https://twitter.com/seirinkogeisha/status/966485502546161665
⑦青林堂『月刊漫画ガロ』1972年5月号表紙(画・辰巳ヨシヒロ)
⑩青林堂『月刊漫画ガロ』1997年8月号表紙(画・Q.B.B=久住昌之+久住卓也)※休刊号(64年の創刊以来初の休刊、その後も断続的に復刊・休刊を繰り返し、2002年の休刊を最後に今日まで『ガロ』は刊行されていない)
⑪青林堂『月刊漫画ガロ』1983年4月号表紙(画・湯村輝彦)
山崎春美のスーパー変態インタビュー(連載第1回/遠藤ミチロウ編)「逮捕後の変態ロックバンド スターリン 遠藤ミチロウ」
先日、遊撃インターネットの管理人である北のりゆき氏(故・青山正明が編集長を務めた『危ない1号』では“死売狂生”というペンネームで書いていたライターさんで『危ない28号』にも寄稿していた結構スゴイ人)のご厚意により、未入手のスーパー変態マガジン『Billy』および『Billyボーイ』を10冊ほど完全な状態で入手することが出来た。
山崎春美のスーパー変態インタビューは『Billy』1982年1月号から連載が始まっており、第1回は遠藤ミチロウ、第2回は明石賢生、第3回は蛭子能収と、そうそうたる面子が並ぶ。
ちなみに『Billy』が本格的な変態路線に誌面を刷新するのは2月号からで、スーパー変態マガジンのコピーは3月号から見える。
この変態路線前の1982年1月号は、表紙からは割と清廉とした印象を受けるが、ページをめくってみると、ホモトルコや三島由紀夫そっくりさんSMショーなどなど、後の『Billy』の片鱗が存分に掴める内容となっている(それでも十二分におとなしめの内容だし、これに死体や奇形、お約束のスカトロをブッ込んだら完全に後の『Billy』になる)。
さて、このインタビューの冒頭で語られる山崎春美と遠藤ミチロウの邂逅についてであるが、山崎の回想によれば遠藤ミチロウは『HEAVEN』の編集室にコンサートチラシの束を抱えて、いきなり乗り込んできたのだそうだ。まるで群雄社周辺から発せられていた「磁場」のようなものに吸い寄せられたかのように。
ちなみに坂本龍一、町田町蔵、遠藤ミチロウ、佐藤薫らが参加したインディーズ史に残る歴史的名盤『タコ』(山崎主宰のロックバンド「TACO」の1stアルバム)は翌1983年にリリースされることになる。
対談◎根本敬(特殊漫画家)×山野一(漫画家)「いまも夢の中にねこぢるが出てくるんです」
「いまも夢の中にねこぢるが出てくるんです」
山野 デビューの頃の話から始めましょうか。当時、すでに結婚して一緒に住んでいたんですが、僕が漫画を描いてるときに、彼女は仕事を持っていなかったので、ヒマじゃないですか。それで落書きをしていたんです。そのネコの絵が面白かったので、これを漫画にしたら面白いんじゃないかということで始めたのがきっかけです。それを『ガロ』に投稿したら載っけていただいたというのが最初で。当時は漫画家になるとかそういうことはまるで念頭になかった感じでしたね。
根本 最初は名前が違ってたよね。「ねこじるし」。
山野 そうです。適当につけた名前で(笑)。変えた理由も明確なわけじゃないですけど、途中から本人がそっちのほうがいいということで。最初からコンセプト的にやってたわけではなくて、とりあえずできたものを載っけてもらった、よかった、ぐらいの感じでしたね。だから、漫画家としての訓練──私も別に受けちゃいませんけど(笑)──は何も受けてない。描いていたのもペンとかじゃなくて、フェルトペンやマジックで描いてましたし。そのへんは根本さんもよくご存じでしょうけど。
根本 デビュー前から知ってるけど、たまたま旦那が漫画家で、紙の空いたところに描いたネコの絵がいつの間にか独り歩きして、すごく大きくなっちゃったという感じだった。でも、俺にとっては別に区別はないから(笑)。いつの間にか周りが「ねこぢる、ねこぢる」って騒ぐようなっただけで。
山野 根本さんにすれば、「なんで漫画描いてるの?」みたいな感じだったんじゃないですか。
根本 でもね、意外と「なんで?」って感じはしなかった。山野さんと知り合う前から、俺の『花ひらく家庭天国』とか読んでたらしいしね。
山野 あ、僕と会うもうずっと前から根本さんの作品は熟読してましたね。
──山野さんは彼女の絵のどこがいい思ったんですか?
山野 ちょっと口では説明しづらいんですけど、何ていうのかな、尋常ではない何かがあって、無表情なのにかわいい、それでいてどっかに狂気が宿ってる、みたいな部分。
根本 目に見えないものとか、言葉にできないものとか、ね。
山野 同じネコの絵を執拗に描く。ほっとくといつまでも描き続けてるみたいなところも尋常でないものを感じましたね。
根本 それを自分で説明できる子だったら、かえって表現できない世界だよね。
山野 たとえば、初期の蛭子能収さんの、何も考えないで描く人間の顔なんかも、当の蛭子さんが無自覚な狂気みたいなものまで、見る者に伝えたりするじゃないですか。それと似たようなもの、言語化不可能なある種の違和感かもしれないけど、大人に解釈されたものではない生々しい幼児性というか、かわいさと気持ち悪さと残虐性が入り交じった、奇妙な魅力みたいなものがあったんだと思いますよ。
──そのうち、原稿の注文が増えてくるわけですよね。
山野 注文が来るなんてまったく思ってもいなかったから、不思議な気がしましたね。普通、漫画家はほかの出版社に漫画を描くときは、別のキャラクターを作るじゃないですか。でも、うちの場合、『ガロ』を見たいろんなとこから来たのが全部このネコの絵でやってくれということだったので、出版社によってキャラクターが変わるということがなかった。
根本 タイトルが変わっただけでね(笑)。
山野 タイトルも多少、文字が変わってるぐらいで、ほとんどねこぢるナントカですから、よくそれで出版社がOKだったなと思いますね。
根本 ねこぢるじゃなくて「ねこぢる」に仕事が来てたんだよね。
山野 まあ、そういうことだと思いますね。
──彼女の中で「ねこぢる」は、自分だけの作品だったのか、山野さんとの共同作業だったのか、どちらだったんでしょう?
山野 仕事とかにもよりますが、役割みたいなものも描いてる連載によって違いますし。どっちにしろ混じっていたのは確かですね。ただ、漫画好きではあったけど、漫画を描いたことがなかったので、いきなり商業誌で「八ページでこんなものを」と言われても無理なんです。アイディアは当人が出すにしても、それを漫画という形にして、いただいたページ数におさめるという作業は僕がやるという感じでしたね。
根本 漫画ってちょっと特殊ですもんね。面白いアイディアがあっても、それを具体的なセリフや、コマ割りで展開するというのは、小説とも違い、ある種の特殊技能ですよ。
山野 本人は多分、漫画家になろうという意志もないままになってしまったんだと思います。ですから、ある程度、事務性の高い作業は僕が代わりにやるという感じでしたね。
──ねこぢるの漫画のセリフはほとんど書き文字ですが、何かこだわりがあったんですか?
山野 本人が書いた字がなかなか味わいがあると思ったので、「そのままでいいんじゃないの」と僕が言ったのが最初だと思うんです。それで、普通なら鉛筆で書いて写植を入れるようなところをフェルトペンとかで書き込んじゃって、出版社のほうでもそれでいいという感じだったので、そのまま印刷されちゃったんだと思いますね。
根本 それがもう、ごく自然な流れでそのままスタイルとして定着して。
山野 そうです。でも、あんなに原稿が大したチェックも入らず、スイスイ入っていくというのは驚きでしたね。僕なんかエロ漫画誌で描かせていただいて食ってましたけど、「これはおっぱいが小さいじゃないか」とか言われて、「すいません」ってその場ででっかく描き直したりとかしていて、うるさく言われるのが当たり前だと思ってました。ねこぢるの場合、差別表現とかどうしても外せない部分ではあるでしょうけれども、それ以外の制約はほとんど受けてこなかった。許されてる枠内で割と自由にやらせてもらっていましたね。
根本 そういうところをひっくるめて“才能”なんだよね。
年を取ることを異常に嫌っていた
山野 以前、ねこぢるが二の腕の内側の静脈瘤というのかな、もつれた細い静脈のかたまりみたいなものを取り除く手術を受けたことがあるんです。座ったままできる簡単な手術なんですけれど、僕は体に刃物が入るとか、怖くて見ていることができないんです。でも、ねこぢるはずーっと手術の様子を凝視してたんです。医者も妙な顔をしてました。それがすごく印象的で。きっとどんなのが出てくるのか見たかったんでしょうね。そうやってじーっとまっすぐに、ある意味無遠慮に、いろんな物や人を見つめるみたいな性質はありましたね。
根本 「にゃーこ」の目にそれが象徴されてますね。
山野 あるとき、新宿駅で歩いてたんですよ。そしたら、今までおとなしく座ってたプー太郎がいたんですけど、いきなり宇宙語みたいなのをわめきながらまっすぐねこぢるのとこに走ってきて、腕をガツーンとつかんだんです。なぜあの無数に歩いている通行人の中から彼女のところにまっすぐ走ってきて腕をつかんだのかは謎ですね(笑)。
根本 それ、ポイント、絶対に何かあるんですよ、そこに。
山野 あと、ねこぢるって異常に年を取らなかった。容貌もあまり変わらないですけれども、精神的にずーっと子供のままみたいなところがありましたね。年を取ることをすごく嫌ってましたね。
──最後まで、お二人だけで描いていたわけですよね。
山野 そうです。でも、スクリーントーンとか、ベタとか、そういう仕上げの作業みたいなものは主に僕がやってたんで、最後まで働いてるのは僕みたいな感じではありましたね(笑)。
根本 マネジャー兼チーフアシスタント。あと、まかないのオバさん(笑)。
山野 そうなんですよね。
──背景とかは、山野さんが描いてるわけですか?
山野 いや、背景もペン入れは全部彼女がやってますけど、たとえば背景の下書きみたいなものは僕がやる。
根本 だからある意味、世に出た最初からねこぢるは絶頂期のフジオプロの赤塚不二夫先生だったんですよ。山野さんは一人で古谷三敏から高井研一郎から長谷邦夫から何から兼ねてたんですよ、もう全部(笑)。
山野 でも、何かやっぱり持ってるものが僕とは全然違っていたと思いますね。
──根本さんは「ねこぢるブーム」みたいなものをどういうふうにみていたんですか?
根本 ねこぢるブーム! そんなのがあったんですか(笑)。
山野 わかんないですけどね(笑)。
根本 まあ、傍から見れば、東京電力のコマーシャルにキャラクターが使われるようになったり、アチコチで見かけるから、ああ、すごく儲けてるなって思ったくらいですかね。
山野 でも、家賃六万のアパートにずっと住んでましたし(笑)。とくには何も変わりないという感じでしたけど。
根本 だって、それで変わるようだったら、そもそも「ねこぢる」は生まれない。でも、皮肉にも忙しくなったよね。
山野 そうですね。ある漫画を描きながらも次、その次の漫画のネタを練ってるみたいな状態ではありましたね。
根本 いつの間にか気付いたらプロの漫画家になってて、しかも売れっ子の(笑)。
山野 本人の中にも仕事をちゃんとこなしたい、もっとやりたいという気持ちと、もうやめたいというのが両方あった気がするんです。意外と責任感があるんで。でも、やっぱり時間的な制約の中で、背景をもっと描きたいんですけども、減らされていったということはあったと思いますね。元の絵が単純といえば単純なんで、劇画とか描かれてる方よりは早く終わるとは思いますけど。でも、それでも、たった二人でやってますから、できる量というのは限られてきますよね。
──二十四時間、ずっとお二人一緒だったんですよね。
山野 まあ、不健康っちゃ不健康なんですけどね。生活も仕事もみんなその狭いアパートで二十四時間一緒に共にしてるわけですからね。すごく売れてる頃とかでも、近所のコンビニでおでん買ってきて二人で食ってるとか、そんなんでしたから。ただ。僕が仕上げで二日か三日ぐらい徹夜でやってて。起きてきた彼女が「『ジャンプ』」と言うんです。『ジャンプ』の発売日っていうと五時に店頭に並ぶから、朝五時に寒い中急いで『ジャンプ』買いに行くわけです。で、まだコンビニで荷ほどきされていない『ジャンプ』の横で、「まだ? もう五時だよね? さあ早く」という顔で待っとるんですね(笑)。帰ってきて俺が仕事を続けてる横で『ジャンプ』を読んでる。『ジョジョの奇妙な冒険』がお気に入りでした(笑)。まあ、私もヘトヘトですからね、いくらか理不尽な思いはありましたよ。でも、そこで何か言い合いを始めるより買いに行ったほうが早いんで。
根本 でしょうね~、それはねえ~、うん。
遺骨と丸一年暮らす
──ねこぢるさんが亡くなった直後、山野さんはどんな感じだったんですか。
山野 白木の遺骨と丸一年暮らしてました。世間的には非常識な事らしいですが、葬るべき墓が無かったのでいたしかたないです。その後近所の霊園に墓を建て、一周忌の法要の時にようやく墓に入れました。自分はまあ家に引きこもって、持病の椎間板ヘルニアが出た時などは、コンビニの出前で暮らしてました。二百円払うと何でも配達してくれるんですよ。
それから家か二〇〇mぐらいのとこにあるカウンターのみの汚い居酒屋に呑みに出るようになりました。七十過ぎで江戸っ子のおじいちゃんと、三十後半のちょっと天然な息子さんがやっていて、ナイターを見ながら野球をまるで知らない僕に色々教えてくれましたよ。何一つ覚えちゃいませんが(笑)。でもそんなこんながちょうど居やすかったんでしょうね。他に客はめったに来ないので、仕入れた肴をどんどんただで出してくれました。これが当時の主食でしたね(笑)。ところがこの店が、ある日予告もなく潰れてまして。おじいちゃんに何かあったのかもしれません。それから製麵所を兼ねた蕎麦屋兼居酒屋みたいなとこにトグロを巻いてて、ここも客の入りはサッパリで、ただでつまみをくれるのはいいのですが、程なく潰れましたね、やはり(笑)。食べ物の善し悪しにうるさかった店主がコンビニで弁当チンしてもらってるとこに出くわしたのはバツが悪かったなあ(笑)。僕が通う店はなぜかみんな潰れちゃうんですよね、僕が載っけてもらってた雑誌がことごとく潰れたみたいに(笑)。
根本 そこは僕も負けませんよ!(笑)。
山野 まあそんなアル中もどきな明け暮れで、健忘症みたいになっちゃって、人とした約束をみんな忘れてしまうんですよ。何もしないでいるのが良くなかろうというので、貰ったまま放置してたMacを、何だかいじくりはじめました。
──その後、山野さんは「ねこぢるy」として作品を発表されました。それを拝見すると、やはり以前の「ねこぢる」とは作風が違いますね。
山野 そうですね。どちらかというと僕は、側にいて翻訳する係、漫才でいうツッコミ的位置づけだったかもしれない。
根本 そう、そうなんですよね!!
山野 すごく面白い人がいても、その面白さを表現するのが上手とは限らないじゃないですか。だから、その面白さみたいなものを翻訳する係のような位置づけというと、わりと近いかもしれない。
──あっちとこっちをつなぐ人みたいな。
山野 たとえば、「ぶたろうは、のろまだけどおいしいにゃー」みたいな言葉を本人はまるで無自覚に言ってるんです。ブタの「のろま」という性質と「おいしい」という性質のあいだにあるギャップみたいなものは、それを意外に思ってハッとする隣の人間がいないとなかなか捕らえられないんです。本人は無自覚なので、それが面白いと思ってもいないから流れてしまうんです。根本さんもいろんな電波な人と会ってるでしょうけど、それを傍で聞いていて面白いと思う人がいて、通訳しないと、その人はそれがとりたてて面白いと思っていないから、そこで流れてしまいますよね。
根本 そうなんです。
山野 それを拾い上げるのが俺の役割だったんだと思います。
根本 うん(深く頷く)。
幼児を金しばりにするジワッと来る衝撃力
山野 今でも、ねこぢるの夢を繰り返し見るんです。死んだのか、いなくなったのかがたいてい曖昧になってる夢で、ある日、急に帰ってくるんです。それで、家を普通に歩き回って、「どこ行ってたの? 何してたの?」みたいなことを言ってもちゃんとした返事もなく、というか、そんな質問に興味がないって感じで、何日かうちをウロウロしたあと、またいなくなっちゃうんです。冷淡この上ないですよね(笑)。
根本 夢に出てくるんですね。
山野 出てきますね。あと、レイブのようなカルトのような一種独特な雰囲気の若者達が、運河の近くの廃墟のようなビルに住み着いていて、商売をしたり、なにかの装置で化学的な実験をしたりしているんですよ。雰囲気はちょっと異様なんだけどまあ平和なかんじで、雑草だらけの庭にはそこにはいないはずの昆虫や小動物がいたりするんですが、そこにいるんですよね、ねこぢるが。「なんでこんなとこにいるの?」と聞くんですが、まあ適当な受け答えするんだけど、やはりそっけなくて(笑)、結局、事情がよくわからないままに夢が終わる。それもけっこう見ますね。
根本 それはいつ頃からですか?
山野 いや、もう死んでからずっとですね。パターンはいろいろありますけれども、まあ、そっけないってことでは一貫してますね(笑)。
根本 ハーン、成程。しかしわかります、それこそ言葉以前のところで。ところで、うちの息子が三つぐらいの頃かな、テレビのアニメとか見だした頃、ねこぢるのアニメを見せたんですよ。子供だから、退屈だったら飽きたとか、イヤだったらイヤだとか、そういう感情とか表現するでしょう? そうしたら最初から最後まで一時間、固まったまま(笑)。本人、どうしていいかわからなくて。
山野 そうですか(笑)。釈然としないまま見たんですね。
根本 俺も、ちょっと問題あったかなと思ったんだけど、本人が画面を見つめて動かないし、しょうがないから時間が経つのを待つしかなかった(笑)。ねこぢるの漫画は、それぐらいジワッと来る衝撃力があるんだよ。今読んでもまったく古びていないしね。それは十年後、二十年後でも絶対に変わらないと断言しますよ。
所収『ねこぢる大全 下巻』p.790-796(絶版)
「本物」の実感 根本敬
大抵、自殺は不幸なものだ。
だが、例外もある。自殺した当人が類い稀なるキャラクターを持ち、その人らしい生き方の選択肢のひとつとして成り立つ事もタマにはあるかと思う。
ねこぢるの場合がそうだ。
死後、つくづく彼女は「大物」で、そして「本物」だったと実感する。
そのねこぢるが「この世はもう、この辺でいい」と決断してこうなった以上、これはもう認める他ないのである。もちろん、個人的には、数少ない話の通じる友人であり、大ファンであった作家がこの世から消えた事はとても悲しい。が、とにかく、ねこぢる当人にとって今回の事は、世間一般でいうところの「不幸」な結末などではない。
とはいえ、残された山野さんにとっては、とりあえず今は「不幸」である。
何故“とりあえず”が付くかというと、ある程度の時間を経ないと、本当のところは誰にも解らないからである。
ねこぢるの漫画といえば、幼児的な純な残虐性と可愛らしさの同居ってのが読者の持つイメージだろう。それも確かにねこぢる自身の一面を表わしてはいるだろうが、「ねこぢるだんこ」(朝日ソノラマ刊)に載っている俗や目常の遠い彼方に魂の飛んだ「つなみ」の様な漫画は、ねこぢるの内面に近づいてみたいなら見のがせない作品だと思う。まだ読んでないファンがいたら、是非読んでほしい。
年々盛り上る、漫画家としての世間的な人気をよそに、本人は「つなみ」の様な世界で浮遊していたのではないか。
俗にいう“あの世”なんてない。
だが、“この世”以外の“別世界”は確実にあると思う。
ねこぢるは今そこにいる。
(文藝春秋『月刊コミックビンゴ!』1998年7月号より再録)
人物紹介
1967年、埼玉県生まれ。漫画家。高校卒業後、漫画家の山野一と結婚。90年、『月刊ガロ』6月号掲載の『ねこぢるうどん』でデビュー。当初のペンネームは「ねこじるし」で、後に「ねこぢる」と改名。可愛さと残酷さが同居する、ポップでシュールな作風が人気を博す。著書に『ねこぢるうどん』『ねこ神さま』『ねこぢる食堂』『ねこぢるだんご』『ぢるぢる旅行記』『ぢるぢる日記』『ねこぢるせんべい』『ねこぢるまんじゅう』など。1998年5月10日死去。享年31
1961年生まれ。1983年、『ガロ』でデビュー。著書に『四丁目の夕日』『どぶさらい劇場』『混沌大陸パンゲア』『貧困魔境伝ヒヤパカ』など。妻であったねこぢるの死後、「ねこぢるy」として『ねこぢるyうどん』を発表。
1958年生まれ。特殊漫画家、文筆家、その他。著書に『生きる』『亀ノ頭スープ』『キャバレー妄想スター』『因果鉄道の旅』『人生解毒波止場』など。「幻の名盤解放同盟」として廃盤レコードの復刻も手がける。